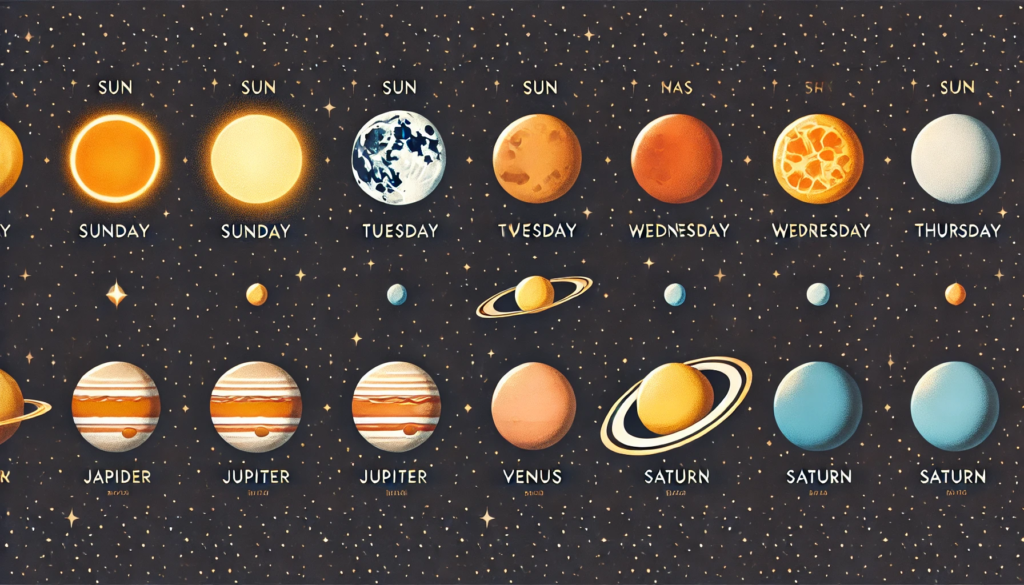
曜日の順番が「日月火水木金土」になった理由は、昔の人たちが空にある 7つの天体(太陽・月・火星・水星・木星・金星・土星)にそれぞれ名前をつけて、それを並べたところから始まります。でも、どうしてこの順番になったのかを、もっと簡単に説明しますね!
- まず、天体を順番に並べてみる
昔の人たちは、次の順番で天体を並べました。
これが 「遠い順」 だと思ってください(地球から見た順番ではなく、宇宙の順番に近い考え方)。
- 土星(いちばん遠い)
- 木星
- 火星
- 太陽
- 金星
- 水星
- 月(いちばん近い)
これが天体の並び方です。
- 順番をどう決めたのか?
天体に 1時間ごとに交代で順番をつけて影響する と考えました。
1日(24時間)は、7つの天体を何度も繰り返して交代するイメージです。
こうして時間を割り振っていくと、次のような順番で「その日の始まり」を決めました。
- 簡単に順番を決めるルール
「その日の始まり」を支配する天体が 曜日の名前 になります。
例:
1番目:最初の1日は 土星 から始まります。だから「土曜日」です。
2番目:次の日の始まりは 太陽。だから「日曜日」です。
3番目:さらに次の日の始まりは 月。だから「月曜日」です。
このルールで進めると、「火→水→木→金」の順番が続きます。
- 覚えやすく言うと…
順番の決まり方を簡単に言えば、昔の人が「遠い順」に天体を並べて、1時間ずつ交代で担当させていった結果、曜日の始まりがこの順番になった、ということです!
まとめ
- 昔の人は、土星・木星・火星・太陽・金星・水星・月の順で天体を並べました。
- 1時間ごとに天体を交代させて「1日ごと」に天体の始まりを決めました。
- その結果、順番が 「土曜日 → 日曜日 → 月曜日 → 火曜日 → 水曜日 → 木曜日 → 金曜日」 になりました!
こうして曜日が決まったのです!





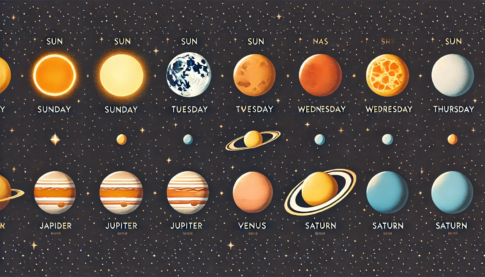


コメントを残す